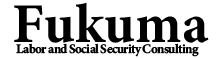<特集>パートタイム・有期雇用労働法について
今回は、今月のニュース・トピックスでご紹介したパート・有期雇用労働法を復習するため、パートタイム・有期雇用労働法はどのような法律なのかまとめてみました。
- 法の目的と背景
少子高齢化に伴う労働力不足を背景に、非正規雇用者(パート・有期)の待遇改善と能力発揮を促進するために施行されました。
また、2021年4月より中小企業にも全面適用され、「公正な待遇の実現」「同一労働同一賃金」の原則を明確化されました。
- 対象となる労働者の定義
この法律で対象となる労働者の定義は次のとおりです。
| 区分 | 定義 |
| パートタイム労働者 | 所定労働時間が通常の労働者より短い者 |
| 有期雇用労働者 | 契約期間に定めがある者(アルバイト・契約社員等含む) |
| 通常の労働者 | 無期雇用かつフルタイムで、正規型の待遇を受ける者 |
- 事業主の義務と対応ポイント
この法律は、2021年に改正されたのですが、その内容についての重要なポイントは次の通りです。
(1)文書による労働条件の明示(第6条)
雇入れ時に通常、労働条件通知書で明示する条件の他に以下の4項目を文書で明示しなければなりません。ただし、労働者の方が求めればFAXやメールでの明示も可となっています。
-
- 昇給の有無
- 賞与の有無
- 退職手当の有無
- 相談窓口の情報(氏名・部署など)
違反時は最大10万円の過料となっています。
(2)就業規則の作成・変更時の意見聴取(第7条)
就業規則の作成又は変更に当たっては、労働基準法第90 条により、労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は労働者の過半数を代表する者)の意見を聴かなければならないこととされています。パートタイマー・有期契約労働者に適用される就業規則作成の場合は、パートタイマー・有期労働者の過半数代表者の意見聴取も努力義務となっています。
無期転換者の規則作成時も同様に意見徴収を行うように配慮します。
- 均等・均衡待遇の確保(第8〜12条)
パートタイム・有期雇用労働法では、パートタイム・有期雇用労働者の待遇について、就業の実態に応じて通常の労働者との間で均等・均衡待遇の確保を図るための措置を講ずるよう規定されています。その際次の判断基準により、不合理でないか、差別的取り扱いがないかどうか確認します。
【判断基準】
- 職務の内容(業務内容・責任の程度)が同じかどうか。
- 職務内容・配置変更の範囲(転勤・異動の有無)が同じかどうか。
【確認事項】
- 不合理な待遇差がないかどうか?
- 賃金・手当・教育訓練・福利厚生など、待遇ごとに合理性を判断します。
② ガイドラインに基づき、職務内容等を比較して検討します。
- 差別的な取り扱いがないか?
判断基準にある2要件を満たすパートタイム・有期雇用労働者は、通常の労働者と就業の実態が同じと判断され、基本給、賞与、役職手当、食事手当、教育訓練、福利厚生施設、解雇 などのすべての待遇について、パートタイム・有期雇用労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されています。
- 通常の労働者への転換推進(第13条)
パート、有期労働者の方の正社員化のための転換制度の整備・周知が努力義務となっています。
具体的には、労働者について、次のいずれかの措置を講じる義務があります。
① 通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者に周知する
② 通常の労働者のポストを社内公募する場合、既に雇っているパートタイム・有期雇用労働者にも応募する機会を与える
③ パートタイム・有期雇用労働者が通常の労働者へ転換するための試験制度を設ける
④ その他通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる
- 説明義務と相談体制(第14・16条)
雇入れの際に、実施する雇用管理の改善措置の内容について説明することや、雇入れ後にパートタイム・有期雇用労働者から求められた場合には、通常の労働者との間の待遇の相違の内容及び理由と、待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務付けられています。
パートタイム・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するための必要な体制を整備することが義務付けられています。
「必要な体制」の整備とは、苦情を含めた相談に応じる窓口等の体制を整備することをいいます(担当者・部署の明示)。
- 苦情処理・紛争解決支援(第22〜25条)
パートタイム・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、人事担当者や短時間・有期雇用管理者が苦情処理を担当するなどして、事業所内で自主的な解決を図ることが努力義務とされています。
事業主は、常時10 人以上のパートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するように努めることになります。
- 実効性確保と行政対応(第18条)
(1) 厚生労働大臣は、パートタイム・有期雇用労働者の雇用管理の改善などを図るため必要があると認めるときは、パートタイム・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます。
(2) 厚生労働大臣は、雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主に対して、勧告をした場合において、事業主がこれに従わない場合には、その旨を公表することができます。
以上、パートタイム・有期雇用労働法をまとめてみました。
アルバイトを含む、パートタイム・有期雇用は、従業員が足りない場合に気軽に雇用できるメリットがある反面、上記の様に労務管理をしっかり行っていく必要があります。
※参考資料:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法のあらまし」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html